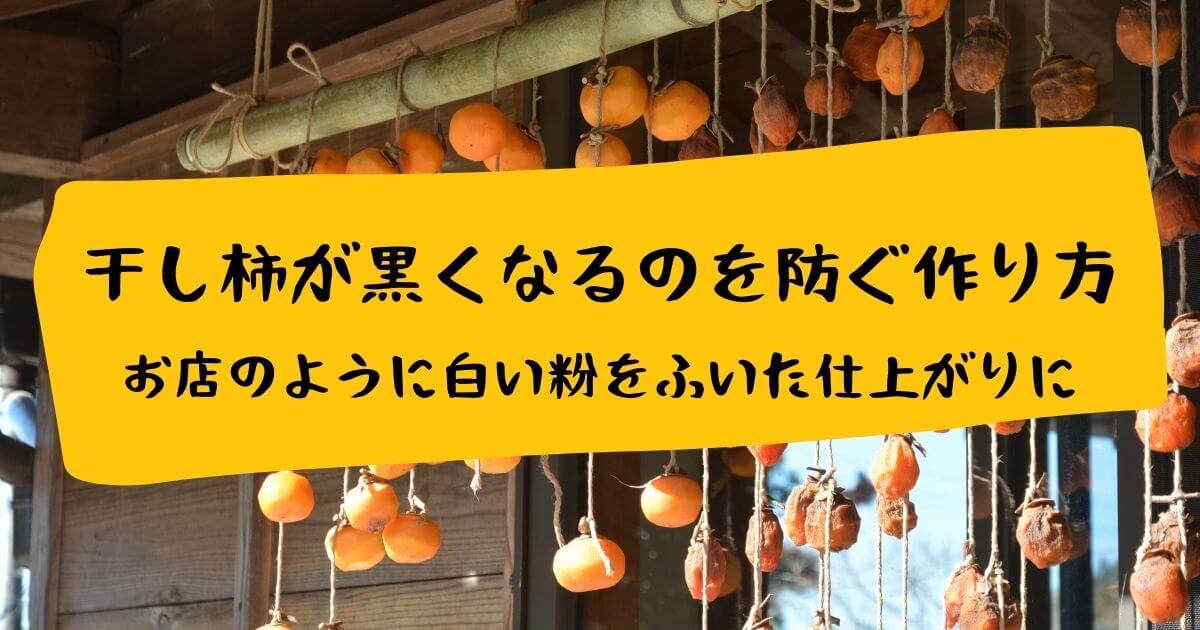秋から冬にかけての風物詩ともいえる干し柿!
お店で売られているものは白い粉のついた飴色の仕上がりなのに、家で作ると黒くなる?
これってもしかしてカビ?カビの心配をせず干し柿が黒くならない作り方を知りたい!
できればお店のように白い粉の付いた鮮やかなオレンジ色に仕上げたい!
この記事ではきれいな見た目のおいしい干し柿の作り方についてまとめています。
- 干し柿が黒くなる原因は?
- 干し柿が黒くならない作り方のコツ
- 干し柿にお店のような白い粉を吹かせる作り方は?
- 干し柿にカビ?カビの見分け方とカビを防ぐ作り方は?
- 黒くならず白い粉をふかせる上手な干し柿の作り方のコツ
- 干し柿の食べごろと上手な保存方法
- 干し柿は体に悪い?干し柿に含まれる栄養は?
干し柿が黒くなる原因は?

家で作る干し柿は画像のように黒くなりがちです。
これはこれでおいしいのですが、お店のような鮮やかなオレンジ色に作ることができたらなと思いますよね。
干し柿が黒くなる原因はズバリ、干し柿に含まれる「タンニン」という物質です。
タンニンとはお茶に含まれるカテキンと同じ物質のことで、渋柿の渋みの原因物質でもあります。
甘柿を切ると黒い点々が見られますが、あれがタンニンです。
甘柿に含まれるタンニンは水に溶けない形の物なので食べても渋みは感じません。
ところが渋柿に含まれるタンニンは水に溶ける形の物なので、そのままかじると唾液に溶けだして渋みを感じます。
渋柿を干すことによってタンニンは水に溶けない形になって甘く食べられるようになるんですよ!
干し柿が黒くならない作り方は?

干し柿の乾燥状態が悪いと渋柿の中に含まれるタンニンが表面化してくるため干し柿が黒くなってしまいます。
干し柿が黒くならないために重要なポイントは3つ!
- 熟し始めていない渋柿を使うこと
- 干す前に塩を入れた熱湯にくぐらせること(5~10秒)
- よく揉むこと
この中で最も重要なのは何と言ってもよく揉むことです!!
揉み始める時期が早すぎても黒くなりやすいので、表面が乾燥し始める10日~2週間ごろを目安によく揉みます。
1個ずつ丁寧に、最低2分以上かけて柿の中身をつぶすイメージで中が均一な餡子のようになるよう揉みこむことが大切です。
そのまま干した渋柿はただの素材、よくよく揉みこむことによって黒くならずにお菓子のように甘くてトロトロになるのです。
黒くなった干し柿は食べられるの?

黒くなってしまった干し柿は食べられるのでしょうか?
画像のように干し柿の全体が黒くなってしまう場合や、部分的にタンニンが染み出して黒いまだら模様のようになってしまう場合があります。
いずれの場合でも、味には遜色ないのでそのまま食べて大丈夫です♪
ちなみに…お店で売られている干し柿は硫黄燻蒸という処理が施されているため本当にきれいなオレンジ色になるのですが、家庭では硫黄の扱いが難しいことからおすすめはできないです。
硫黄燻蒸はしなくてもきれいな色に仕上げることはできますし、うまくいかなくて黒くなってしまっても味には遜色ないので是非気にせず食べてくださいね。
干し柿にお店のような白い粉をふかせる作り方

家でもお店で売られているように白い粉をふいた干し柿が作ってみたいですよね。
そもそも白い粉の正体は?白い粉をふかせる方法について紹介します。
干し柿の白い粉の正体は…?
干し柿の表面についている白い粉の正体は「糖分」です。
カビと間違えてふき取る方もたまにいるのですが、これは柿に含まれる糖が結晶化したものなのでそのまま食べて大丈夫!
むしろおいしくできた干し柿の証だと言ってもよいものですよ。
地域によってはそのまま干すだけで白い粉をふく場合もあるのですが、実際のところそのままでは白くならないことが多いです。
なぜなら、白い粉をふかせるには寒さが重要で、大体10度以下の温度で2週間以上干さないといけないです。
でも温暖化の影響もありなかなかそのような環境を整えるのが難しいんですよね。
干し柿に白い粉をふかせるコツは?
自然に白い粉を作るには東北などの寒冷地で11月中旬以降、それ以外の地域なら12月に入ってからなら出来るかもしれない…という感じです。
でも実は人工的に白い粉を出す方法もあるので紹介しますね。
たわしでこする方法
- 干してすぐ、少し乾燥し始めたらたわしで優しく表面をこする
- 3日くらい経って乾燥が進んだら、身を崩さないよう気を付けながら、たわしでもっと表面をゴシゴシする
- 完成するまでマメにゴシゴシを繰り返す
- 完成しても白い粉がない場合には、冷暗所で一晩おいておくと白くなる
ガーゼに包んでこする方法
完成した干し柿をガーゼに包んで、柿同士をこすり合わせて軽く揉むという方法でも白い粉を作ることができます。
揉み終わったら広げて凍らない冷所で保管しましょう。
冷凍する方法
出来上がった干し柿をラップでしっかりとくるみ、ジップロックなどに入れて冷凍する方法もあります。
自然解凍後に時間がたつと白い粉が出てきますよ。
干し柿の保管方法としても冷凍は便利なので、この方法もありだと思います♪
新聞紙に並べる方法
箱に新聞紙を敷き詰め、その上に重ならないように出来上がった干し柿を並べます。
量が多いときは並べた柿の上に新聞紙をしいてさらに柿を並べて、10日ほど凍らない冷所に置いておくと白い粉が出てきます。
昔は新聞ではなく藁を利用することが多かったのですが、最近は手に入りにくいので新聞がおすすめです。
干し柿にカビ?カビの見分け方とカビを防ぐ作り方
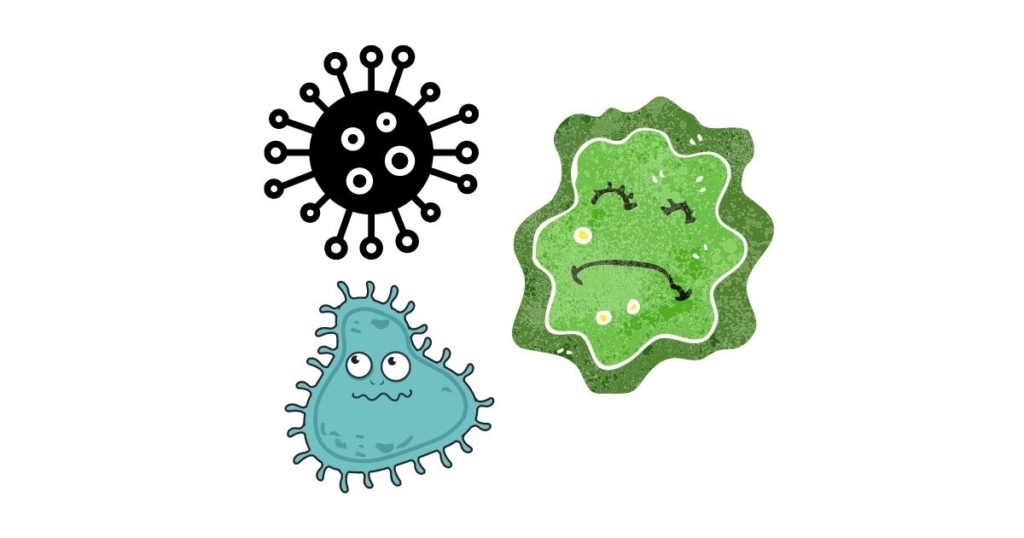
干し柿にカビが生えてしまった?
カビの見分け方と、カビを防ぐ作り方を紹介します。
干し柿についているのはカビ?
まず簡単なカビの見分け方として、色があります。
緑色や青色をしている場合、カビで間違いありません。
少量ならその部分を取り除いて食べても大丈夫と言われていますが、たくさんついてしまった場合には捨てたほうが無難です。
判断が少し難しいのが白いカビです。
白い粉がついているのは甘い干し柿の証拠だと述べてきましたが、カビはダメです!
その見分け方のコツは、白い部分が綿のように見えたりカビ臭がする場合にはカビです。
そして、干し柿の乾燥中に白いものがついた場合にはカビの可能性大!
糖が結晶化した白い粉は完成間近や干し終わってから出ることがほとんどなので、見分けの参考にしてくださいね。
干し柿のカビを防ぐ作り方のコツは?

干し柿のカビを防ぐ作り方のコツはこちら!
- できるだけ寒くなってから作ること(目安15℃以下、11月くらいから)
- 干す前に塩を入れた熱湯にくぐらせること
- 柿同士がくっつかないように干すこと
- 雨の日は室内に入れること(特に最初の3日間に雨に当たると危険)
- 念には念を入れるなら、アルコール35度の焼酎を含ませたペーパーで定期的に柿を拭くと安心
 あんな
あんな私は焼酎で拭くところまではやらないことが多いですがカビが生えたことはないです。雨に当たって心配な時などだけでも大丈夫かも!
黒くならず白い粉をふかせる上手な干し柿の作り方のコツ


ここまで、干し柿を黒くならないように作るコツや、白い粉をふかせる方法、カビを生やさない方法について述べてきたので、上手な干し柿の作り方をまとめたいと思います。
- 熟し始めていない渋柿を使って、15℃以下の日が続くようになってから作る
- 皮をむいて、ひもで結んだら塩を入れた熱湯に5~10秒くぐらせる
- 直射日光の当たらない場所に柿同士がくっつかないように干す
- 少し表面が乾いたらたわしで優しくこする
- 3日経ったら実を崩さないように気を付けてたわしでゴシゴシこする
- 10日から2週間経ったら1個ずつ丁寧に揉んで中身が均一なあんこのようにする(1個当たり2分以上揉む)
- 形を整えてさらに1~2週間干す(定期的にたわしでゴシゴシ)
※雨の日は室内へ。特に最初の3日間は絶対に雨に当てないように



見た目にこだわるならこんな手順になりますが、めんどくさい!という場合にはカビだけ気を付けてそのまま干しても十分おいしいです 笑
柿がたくさんある場合には皮むき器を使うと便利ですよ。
ひもの両端に柿を結んで二つ一組で柿をつるすことが多いですが、たくさんある場合には専用の短冊を使うとラクチンですよ。
枝をひっかけるだけでOKで、雨の日の移動も簡単です♪
干し柿の食べごろと上手な保存方法


干し柿を干したはいいけれども、食べごろがわかりにくいという声をよく聞きます。
干し柿の完成の見分け方と、上手な保存方法についてまとめます。
干し柿の食べごろは?
干し柿の食べごろに関しては、柿の大きさと好みにもよるので一概には言えないのですが…
よく揉んで作る場合、小さめの柿なら2週間くらいから食べられるようになりますが、3週間程度を目安に考えると良いでしょう。
揉まずに作る場合には1か月から40日が目安になります。
あまり長く干していると硬くなってしまうので、時期が来たら取り込むようにしましょう。
干し柿の保存期間と保存方法は?
よく干した干し柿の場合には常温で保存することが可能です。
キッチンペーパーなどに包んで風通しが良いところで保管しましょう。
とはいえ、どんどん水分が抜けていくので3日程度で食べるのがおすすめです。
中身がトロトロの干し柿は腐りやすいので常温保存はおすすめできません。
冷蔵庫に入れる場合には、一つずつラップで包んでジップロックなどに入れましょう。
大体1か月程度は保存できますよ。
でも長期保存するとニオイ移りなどもあるので長期保存するなら冷凍が良いと思います。
冷凍なら3か月は持ちますし、冷凍によって白い粉をふかせることも出来ておすすめです。
食べるときは自然解凍してくださいね。
干し柿が黒くなるのを防ぐ作り方!白い粉をふいたお店のような仕上がりに まとめ


干し柿が黒くならずに、お店のように白い粉をふいたきれいな仕上がりになる作り方についてまとめました。
とはいえ、家で食べる分にはそこまで神経質に作らなくても大丈夫!
まずは気軽に干し柿づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか♪